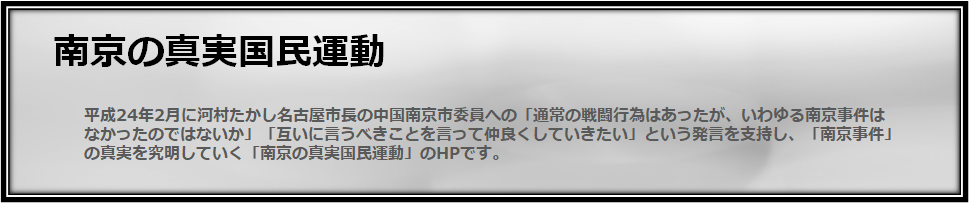ミャンマーのセイン・ウィン国防相が9月21日に防衛省を訪れ稲田朋美防衛相と会談した。その席でセイン・ウィン国防相はこう繰り返し語った。
「ビルマ独立義勇軍と日本軍が英国の植民地支配を打ち倒した。日本兵と日本に対し、いつも感謝している」
昭和16年2月、鈴木敬司大佐を長とする南機関が発足した。鈴木大佐のほか9人の機関員からなり、目的はビルマ(現在のミャンマー)を独立させることで、そのため兵器を供与し、幹部要員に軍事訓練をするというものである。さっそく工作が始まり、アウン・サン(アウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相の父親)はじめ独立の志士が次々と日本にやってきた。やがて海南島で軍事訓練が始まり、大東亜戦争開始とともに彼らはビルマに入った。そのうちの一人であるネ・ウィンはゲリラ工作の班長を務め、日本軍の快進撃もあって、昭和18年8月、ビルマは独立を果たした。アウン・サンは首相の座に就いた。しかし日本が大東亜戦争に敗れたため、イギリスがビルマに戻ってきて再び独立の戦いが始まる。このとき独立義勇軍は軍艦マーチを奏で、日本式号令で戦い、昭和23年1月にあらためて独立を勝ち取った。
独立の志士の多くはビルマ政府の中枢に入るが、彼らは南機関員が心から独立を願っていたことを知っていた。賠償問題が起きたとき南機関員が両国の橋渡しを務めたのはビルマ政府が彼らを信頼していたからである。昭和56年、大統領となっていたネ・ウィンは鈴木機関長夫人以下7名の日本人を招待し、勲章を贈った。これも南機関員が独立のためどれほど働いてくれたか知っていたからである。そういった評価がその後も変わることなく、今回のセイン・ウィン国防相の発言となったのだろう。
9人の機関員の1人が野田毅大尉である。野田毅は、陸軍士官学校を卒業すると、南京攻略戦に参加した。やがて南機関の一員としてビルマ独立に奔走する。アウン・サンは面田という日本風の名を持ち、野田毅と面田の交流は「野田日記」(展転社刊)に描かれている。ビルマ独立義勇軍は、鈴木敬司司令官、野田毅参謀長、アウン・サン高級参謀という陣容から成っていたのである。
戦後、野田毅は百人斬り競争をしたとして南京で銃殺刑となった。処刑は戦時宣伝と復讐がからみあったもので、まったくの濡れ衣であった。野田毅が処刑されなければ、昭和59年に鈴木未亡人とともにビルマに招待され、勲章を受けていただろう。
平成13年、濡れ衣を晴らしたいという遺族の気持ちを知った稲田朋美弁護士は法廷に訴えた。野田毅の生家のある鹿児島錦江町に足を運び、野田毅の墓に線香をあげ、錦江町の町民に野田毅が無実であることを訴えた。いわゆる百人斬り訴訟で、稲田弁護士はこの訴訟を一から進めた。結果として法廷で濡れ衣を晴らすことはできなかったが、4年にもわたり尽力した。
あれから10年、稲田弁護士は稲田代議士となり、いまは防衛大臣の地位に就いている。セイン・ウィン国防相が稲田朋美防衛大臣に繰り返した言葉を野田毅はどんな気持ちで聞いているだろうか。