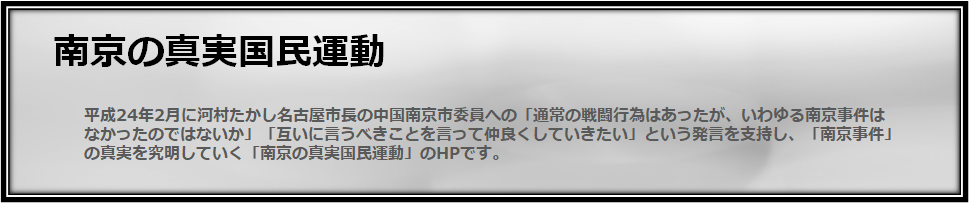昭和十二年十一月から十二月にかけ「毎日新聞」に百人斬り競争が報道され話題を呼んだ。昭和四十七年になると、鈴木明が「『南京大虐殺』のまぼろし」で取りあげ、再び大きい話題となった。平成十年には遺族が法廷に訴えて三度話題となった。このように百人斬り競争は長い間世間の耳目を集めたが、戦中と戦後では話題の中身が違っている。戦中は武勇伝として話題になったのだが、戦後は実際に百人斬り競争はあったのか話題となり、そのときは激しい論争を巻きおこした。戦後の論争史のなかでこれほど長く話題となったものは類を見ず、いまだもって続いている。
その百人斬り競争について、これまで発表されたものがまとめられ、このほど刊行された。渡辺晋太郎著「関西大学図書館資料紹介」(発行所 株式会社ユニウス 大阪市淀川区木川東4-17-31 2315円と消費税)で、著者は関西大学の図書館に勤める職員である。「関西大学図書館資料紹介」とあるように、もともとは関西大学の蔵書のなかから二十五点を選び、その梗概を関西大学生活協同組合発行の「書評」に紹介し、一冊の本にまとめたものである。その最後に「番外編」として、書き下ろし「世紀の遺書」が加えられたが、それこそが百人斬り競争の集大成なのである。
昭和十二年の新聞記事から始まって、昭和四十六年に話題となったときのそれぞれの主張、平成十年の訴訟での対立点まで、重要なものはすべて収められている。半世紀以上もの間論争になっただけにその資料は膨大な量にのぼるが、著者はそれらをたんねんに集め、収めるべきものとそうでないものに分け、解説をつけた。それだけに七百五十頁にも達し、この本の85パーセントを占めている。「関西大学図書館資料紹介」というより「百人斬り競争全資料」というほうが適切である。
手に取ってみると、資料を収集したエネルギーにも感心するが、取捨選択も適切である。資料中心であるが、読み物のように読めるのは、取捨選択が的を射て、付された解説が適切だからであろう。
十年前に主任弁護士としてこの訴訟と関わった稲田朋美自民党政調会長は、昨年、百人斬り競争について「朝日にはぜひもう一度再精査をお願いしたい」と述べている。
遺族のあいだでは、最近、「法曹界がまともになりつつある。もう一度、訴訟に持っていって判断を求めたい」という声があがっている。
長い、激しい論争からいえば、このような著述が出てもおかしくはなく、訴訟から十年、価値ある本が刊行されたというべきであろう。