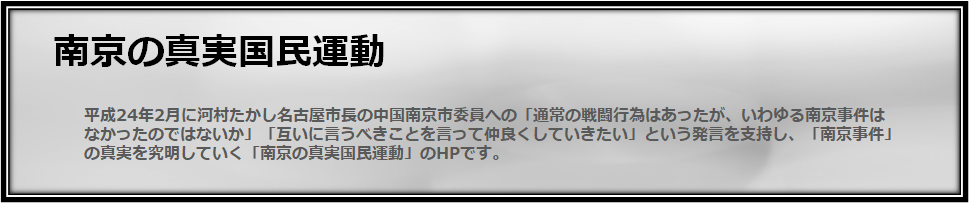三月二十日、展転社取り立て訴訟に判決が下った。判決は展転社の主張が全面的に認められる完全勝利だった。
発端は平成十二年のことで、南京事件の犠牲者だと称する夏淑琴が『「南京虐殺」への大疑問』を著した松村俊夫さんと出版社の展転社を中国で訴えた。この本により名誉毀損されたというもので、間もなくすると松村俊夫さんと展転社に南京地方裁判所から呼び出し状が送られてきた。しかし、南京事件というものは中国が国家として認め、その日を祈念日に決めており、司法が国家に隷属している中国で南京事件に関しまともな裁判が行われるはずない。松村俊夫さんと展転社が無視していると、平成十八年、南京地方裁判所は松村さんと展転社に二千三百万円を支払うよう判決を下した。
二千三百万円とは中国人にとって生涯の収入である。いかにも中国らしいやり方だと感心する人もいれば、驚く人もいたが、中国はそれで満足したのだろう、ともあれこれで一段落した。
ところが八年経った平成二十四年、突然、夏淑琴は二千三百万円の取り立てを命ずるように日本の裁判所に訴えて、いわゆる展転社取り立て訴訟というものが始まった。
日本で下りた判決が他国で執行されたり、他国で下りた判決が日本で執行されることはよくあるが、それは相互保証のある国の間でのこと。かつて日本で下りた判決を中国で執行を求めたとき、中国の最高裁判所は認められないという判断を下し、日本と中国の間に相互保証はない。
そもそも、執行される判決は公序良俗に反していけないが、生涯収入に及ぶというべらぼうな慰謝料を命じている。また、執行できる時効も過ぎている。南京事件を持ちだして日本に揺さぶりをかける訴訟だと考えられたが、最近の日本の法曹界を考えると、執行が認められるという万が一も無視できない。そのため、これまで南京事件の訴訟に携わってきた高池勝彦弁護士をはじめとする弁護士が集まってただちに弁護団が結成された。また南京事件に強い関心を持っている人たちを中心に被告と弁護団を応援しようと「展転社を支援する会」が結成された。
日本の判決が中国で執行されたことはないだけでなく、中国で下りた判決が日本で執行されたこともない。今回の判決は、下りるとすれば判例に記載されるようなもので、そのため裁判所は、相互保証が認められるような資料があれば提出するよう夏淑琴側に求めた。夏淑琴側は提出すると答えながらなかなか提出しない。結果からいえば、そのような資料などなかったのだが、そのため、双方の主張は出尽くしたにもかかわらず、二年半もの間判決が下されなかった。
このようなことから展転社や支援者たちは勝利を確信していた。二十日の法廷で「原告の主張を棄却する」と述べられると、法廷には、一斉に万歳の声が上がり、拍手が鳴りひびいて止まなかった。二千三百万円というべらぼうな執行は認められなかったのである。
閉廷後、近くの弁護士会館で説明会が行われた。傍聴に来た四十人ほどの支援者に対して弁護団から、相互保証がないので原告の首位長は認められないという当然な判決だった、と解説が行われ、そのうえでそれぞれの弁護士が感想を述べた。
荒木田修弁護士は「もし原告の主張が認められれば、中国で都合のよい判決が次々下り、それが日本で執行され、日本は危機に陥る。本来は日本の大企業が注目すべき訴訟であった。また、原告の主張が認められれば、反日弁護士の間で売国ビジネスが誕生してしまうが、それも阻止できてよかった。できれば、中国の司法が国家や中国共産党のいうなりで裁判所の体をなしていないということで棄却にしてほしかった」と言えば、尾崎幸廣弁護士は「時効を挙げて棄却せず、相互保証という根拠を挙げていたので、完全勝利と言えるでしょう」と述べた。最後に、高池勝彦弁護団長が「この案件は最高裁判所まで行くと東京地裁の裁判長は言っており、原告側も引っ込みがつかない。判決が変わることはないが、これで終わりにはならない」と話した。
裁判は東京高裁でも続けられる。