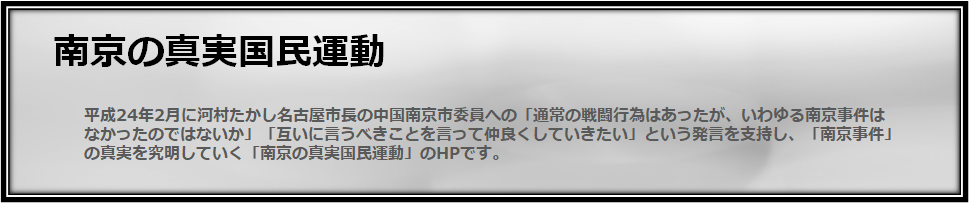11月9日、「南京裁判」展転社の口頭弁論が東京地方裁判所で開かれました。前回の口頭弁論では、双方がこれまでの主張を総括的に述べ、口頭弁論は一段落しました。その際、夏淑琴の代理人から、日本の判決が中華人民共和国で実行されたケースがあるので後ほどその証拠を提出します、と発言がありました。それまで展転社側は、日中間に相互保証はなく、中国で下った判決は日本で強制されないと主張してきており、それに反論しようとしたものです。ともあれ、中華人民共和国で実行されたという証拠が夏淑琴側から提出され、今回の口頭弁論で結審になると予想されていました。ところが前回の口頭弁論から2か月経ちましたが証拠は提出されませんでした。夏淑琴側はさらに証拠を探す時間を要求しましたためこの日で結審とはならず,法廷は来年2月中旬まで提出するよう求めたうえ、改めて3月7日に口頭弁論を開くことにしました。
前回同様、傍聴者はほとんど展転社を支援する人たちで、口頭弁論のあと、近くの弁護士会館で説明会が開かれました。この訴訟は展転社とともに松村俊夫さんも訴えられていましたが、松村俊夫さんは9月28日に亡くなり、冒頭で松村さんへ黙祷が捧げられました。亡くなる前、松村さんは支援者にメッセージを送っており、ここに転載いたします。
いわゆる南京取り立て訴訟支援者の皆様へご挨拶申し上げます。
ご承知の通り私は、展転社藤本社長の戦友として弁護団の先生方のご尽力を得て、実質上の原告である代理人渡辺弁護士と十数年来闘って来ました。その間、法廷や支援する会でお目にかかった方々も多いかと思います。
ところが六月はじめに思いもかけぬ病を発症し、いまでは見る影もなき一介の素浪人のようになってしまいました。この間の事情については、藤本社長から説明をお願いしたいと思っています。
しかし幸いにも夏淑琴による南京法廷への提訴に始まって以来、それまで李秀英事件も含めて、ありとあらゆる資料を用いて書き上げた陳述書形式の二つの論文があります。
もともとこれらは、国際民事訴訟法の解釈を争点とする今回の裁判にはなじみません。しかし、渡辺弁護士は少しでも自分に有利になるとの浅はかなつもりで、東中野裁判勝訴のみならず、李秀英裁判勝訴の判決文を証拠書類として出してきました。この意義については支援する会の会報第三号や国民新聞にも書きましたのでご存じの方も多いと思います。
私の南京事件研究は、李秀英、夏淑琴は傍流で、論文は昨年の『正論』二、三、五月号をはじめ、南京学会への論文『明日への選択』、国民新聞など多岐にわたります。それを知らない渡辺弁護士は私を浅学の徒と思い込み、中国の威を借りて踊っているだけです。ウソも百遍言えば本当になるとばかり、何の裏付けもない中国人発言を後生大事に守っているだけです。
特に夏淑琴は当時のことは全く記憶になく教えられたことに過ぎないとの本人の告白がでたあとも相変わらず夏淑琴供述調書という書証を臆面もなく法廷に提出する鉄面皮の持ち主が我々の相手です。私は売国奴と思っています。
もはや私に皆さま方に伍して闘う力を失いました。
願わくばこれまで私が各所に書いてきたことを参照頂き、中国人の利益のみ考え私としかも家内の生活を潰そうとしている人物の糾弾に力を貸していただくようお願い申し上げます。
六百万支払うというストレスに負けたとは思いたくありませんが、現実はその通りです。場合によっては、これが遺書になるかもしれません。有難うございました。
これが松村俊夫さんが支援者に送ったメッセージです。
黙祷に引きつづき、高池勝彦弁護団長をはじめ、荒木田修、尾崎幸廣、山口達視、田中禎人、辻美紀の各弁護人から意見や見通しが述べられました。
傍聴者からもさまざまな意見や疑問が発せられました。なぜこのような常識外れの訴訟が起こされるのか、代理人たちはどのような人種なのか、といった疑問が発せられました。
前回の口頭弁論で展転社側は、もし取りたてが認められたなら中華人民共和国による日本からの収奪が始まる、と主張しましたが、それに対し今回夏淑琴側は、中華人民共和国で司法は独立しており、そのようなことは杞憂だ、と反論しました。ところがその主張から3日後、中国共産党の3中総会が閉幕後にコミュニケが発表され、6項目のうちのひとつに「独立した公正で健全な司法制度を整備」とあり、司法が独立していないことを中華人民共和国が認めているのです。このゆうに渡辺弁護士たちの主張はすべて奇弁そのものなのです。
ともあれ、口頭弁論が展転社側に有利に進んでいることもあり、活発な意見が発せられ、有意義な説明会となりました。
次回は来年3月7日(金)、東京地方裁判所で午前11時から開かれます。
東京地方裁判所へは地下鉄が便利です。霞が関で降りるとすぐ東京地方裁判所があります。次回の傍聴は抽選がありませんから、直接、一階の103号室にお越しください。
口頭弁論が終われば、弁護士会館で説明会が行われます。12時30分までにはすべて終了する予定です。