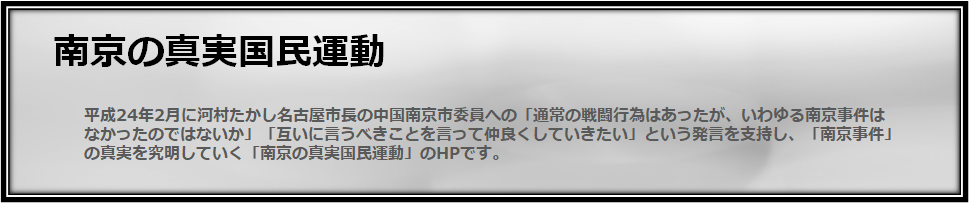五月十八日、興亜観音の平成二十六年例大祭が行われた。五月晴れのもと、相模湾の水面に輝く光を受け、住職はじめ参列者は清々しい気持ちで臨み、およそ三十分にわたり厳かに取りおこなわれた。
興亜観音の建立を発願したのは、南京事件で刑死した松井石根大将である。
松井石根大将は、若いときからアジアの国々は協力していくべきという考えを持ち、昭和八年には大亜細亜協会の設立に尽力していたが、昭和十二年八月、上海派遣軍司令官に任命され、本来なら手を携えるべき中国と戦うことになった。また松井大将は、観音様の熱心な信者で、出陣にあたり観音像を寄進されると、陣中まで持っていった。
このようなことがあって凱旋帰国すると、陣中に持っていった観音様を祀って戦死した将兵の霊を弔おうと思いたった。
その思いに賛同した人々の寄進で熱海の伊豆山に観音堂が建立されることになり、新たな観音像も作られ、昭和十四年冬に落慶、翌年春、開眼式が行われた。
観音堂には、日本の戦死者と並んで中華民国の戦死者の位牌が置かれ、新たな観音像は激戦が行われた上海大場鎮の土を取りよせ作られ、興亜観音と名づけられた。
東京品川から伊豆山の麓に住まいを移した松井大将は、それ以来、毎日、小高い山に登って参拝するのを日課とした。
そのような松井大将の精神からいって南京事件のような不祥事が起こるはずはなく、当然のことながら松井大将が事件があったと知ったのは戦後になってからである。そして言うまでもなく最後まで事件を否定していた。
松井大将は、戦争犯罪容疑者として巣鴨に出頭するまで興亜観音の参拝を続け、出頭するとき伊丹忍礼に堂守りを頼んだ。伊丹忍礼は、観音堂が建立されたとき、松井大将の要請により住職になった僧侶である。
松井大将が死刑の判決を受けたため、伊丹忍礼はそのまま観音堂を守ることとなったが、敗戦の衝撃により参拝者は激減、檀家があるわけでなかったため伊丹家の生活は困窮をきわめた。
それでも松井大将のかつての部下や大アジア主義に共鳴した人たちによる参拝がほそぼそと続き、世が落ち着くと、参拝者は増え、興亜観音を支えるためのさまざまな活動も始まった。例大祭も、今年の参列者は十数名だったが、少ないときでも数十名、多いときは数百名が集まった。
伊丹忍礼は死ぬまで堂守りを続け、忍礼亡きあとは妻の妙眞がかわりを務め、現在は夫妻の三女である妙浄が跡を継いでいる。今年の例大祭も妙浄尼が法要を行った。
観音堂や観音像は建立から七十四年を経ているが、それほどの傷みは見られず、建立された当時を髣髴させている。途切れることなく例大祭が行われてきたことは松井大将がもっとも願っていたことであろう。毎年五月十八日に行われる例大祭には松井大将の志を理解する人なら誰でも参列できる。